|
パン屋さんのフィールドワーク・その4 「かすたねっと」の名の由来 〜練馬の手作りクッキーのお店〜
|
武蔵大社会学部:小早川梓乃・田辺智子・松岡明佳・山崎加奈子
取材日:2003年6月4日
 |
 |
| お店の看板「かすたねっと」 上部の「こねている手」に注目! |
楽器のカスタネットによく似ている! |
| 1 手作りクッキーの店「かすたねっと」の風景 |

|
練馬駅から徒歩2分、練馬文化センターのすぐ裏で「クッキーいかがですかー?」という元気な声が聞こえ、そちらのほうへ向かってみると、それは手作りクッキーの店『かすたねっと』の従業員さんたちの声でした。 『かすたねっと』では、知的障害をもった方(以下「利用者」という。)と職員の方がクッキー・ケーキの製造から袋詰め、包装、販売までをすべて行っていらっしゃいます。今回は『かすたねっと』の店長をしていらっしゃる矢吹良子さんにお話を伺いました。 |
|
(1)『かすたねっと』について 営業時間はAM9:00〜PM6:00(木・日・祝祭日休業)。そのうち利用者の方の勤務時間はAM9:00〜PM5:00くらいで職員の方はだいたいPM8:00くらいまで残って仕事をされているそうです。利用者と職員の人数構成は、利用者15人に対し職員4人(うち1人は非常勤。)で働いています。 (2)利用者の方について 『かすたねっと』で元気に働く利用者の方々はどのような方たちでしょうか。まず、「利用者の方々はどの辺りに住んでいらっしゃるのか」というところから聞いたところ、利用者の方はほとんどが西武線沿線に住んでいらっしゃるということでした。利用者のみなさんは学校の先生や知人の紹介を通じて、学校卒業後に実習をうけ、就職という流れで働き出し、勤務期間は一番長い人では17年間で毎年1人くらいずつはいっているとおっしゃっていました。 矢吹さんのお話では、利用者の方の仕事のできは一人一人異なっているそうです。また、利用者のみなさんは職員の方にどんなに怒られても、「やめろ」と言われても、やめずに続けているとおっしゃっていました。それはお菓子作りが大好きだからこそ続けられることなのです。 (3)『かすたねっと』の雰囲気(利用者と職員の雰囲気)について まず、店内に入って私が受けた第一印象は「とにかく明るい!活気がある!」ということでした。みなさん明るく挨拶をしてくれ、笑い声も聞こえてきました。 店内での作業の順としては①生地作り②押しだし③クッキーの形を整える・生地に混ぜる具材をいれる④焼く⑤分量を量って袋詰め、という感じでみなさんがそれぞれ分担して仕事をされていました。 矢吹さんのお考えでは、利用者の方が「疲れないよう、働きやすいよう」に利用者の方の状態をみながらメリハリをつけて常に気を配っているそうです。 (4)『かすたねっと』のメニューについて 『かすたねっと』のクッキーは全11種で310〜350円、ケーキは全4種で510〜1000円程度でした。私たちはレモン・ナッツ・チョコミント・かすたねっとの4種のクッキーを試食させていただきました。どのクッキーも甘すぎることなく何枚でも食べられそうなほどおいしいものでした。かすたねっとではメニューの立案は代表の方たちが行っていて、1年に1つは新メニューが出せるように努力されているそうです。 |
| 今回、私たちは試作段階の「ジンジャー」のクッキーを試食させていただきました。このクッキーはショウガがきいていて、今まで食べたことのないような新鮮な味でとても印象的でした。店の奥のほうにはクッキー用のパッケージが置かれていて、この箱の組み立てなどはボランティアの方がやり、箱についているひとつずつ色・形の違うクマのぬいぐるみはすべて手作りだそうです。 |

|
|
(5)矢吹さんからみる利用者の方々 最後に、矢吹さんはこうおっしゃっていました。 「最初は何もできなくても、仕事を覚えていくことで利用者たちに自信がついてくる。これが一番大切なことなんです。これには根気と継続が必要だが、まずは自信をつけさせたい。」 矢吹さんは利用者のみなさんが生き生きと明るく働けるよう、「根気と継続」をもって日々努力を重ねていらっしゃいました。 |
| 2 「かすたねっと」の課外活動と外事情 |
|
(1)かすたねっとの宣伝活動 宣伝・広告の手段として年4回、広報誌『かすたねっとNEWS』を発行しているそうです。その編集人は、こちらの代表の矢吹一夫さんです。ここには、お店で作られているクッキーの紹介はもちろん、福祉事業について、作業所に体験実習をしにきた学生の体験記などが掲載されています。また、2002年冬には練馬区の21世紀幕開け記念事業のひとつとして、『ねりまの名品21』に選ばれました。これは利用者の皆さんが、ひとつひとつ丁寧に心を込めて手作りし続けている努力の結果なのでしょう。かすたねっとのクッキーは、お中元やお歳暮など、贈り物にも良いそうです。 |

|
|
(2)地域の人々とのつながりはどのようにあるか ここ10年間くらい、練馬区のつつじ祭・照姫祭や各バザーなどに参加しているそうです。そして、この機会に出店し、クッキー・ケーキを販売しています。普段店で販売するだけではなかなか売上は伸びないので、宣伝を兼ねて、積極的に地域の行事に参加することによってそれを補っているそうです。 ⇒地域のつながりは十分あるようなので、それならば他の福祉作業所またはそのような施設同士でも関わり合いを持っているのかと思い訊ねてみると、そういった 横のつながりは残念ながら無いそうです。しかし、年1回障害者施設合同の運動会があり、それには参加しているということでした。(今年は雨天の為中止…) ☆また、かすたねっとではクッキー・ケーキの宣伝も兼ねて、練馬区内の養護学校へ自ら出向き、作業所の説明会をしばしば行っているそうです。そこで、お店に興味を持ってもらえれば、将来かすたねっとで働く次の人材につながるかもしれないからです。 |
|
(3)かすたねっとの野外活動 年4回程、日頃の訓練を兼ねた旅行にいくそうです。海外へは3〜4年に1度の割合で行くそうで、ちなみに前回はハワイ、前々回はスリランカだったそうです。 そして、1996年1月〜8月の間には、利用者の皆さんの親やボランティアの人々も同伴で、羽田(海抜ゼロメートル)から出発し、富士山頂上を目指して登りました。 ・・・しかし、この富士山登頂を達成するまでには、本当に大変だったそうです。 店長の矢吹良子さんのお話では、普段は根気強く真面目に仕事をしている彼らですが、自分たちの親が傍にいるせいか、途中ですぐに弱音を吐いたり、何度も休憩をとろうとしたりで“出来ないのではなく、やろうとしない”甘えが目立っていたそうです。けれども、矢吹さんはそこでいつもよりも厳しい態度で接したとおっしゃっていました。ここで甘やかせば、作業所に戻ったところで何も成長していないことになるからです。 |

|
| 3 新しい「福祉」 |
|
「かすたねっと」のオーナーであり、主に対外的なお仕事、また広報誌の「かすたねっとNEWS」の編集をされている矢吹一夫さん。その矢吹さんに福祉システムと現状について、幾つかお話を伺いました。 (1)福祉システム─新しい福祉 ①ガイドヘルプサービス 知的障害者の方が外出する際に、移動時の介護・補助等を、登録されたヘルパーの方が行うサービス。2003年4月より支援費が導入され「かすたねっと」の皆さんにも推奨しているそうです。 |

|
|
②第三者評価システム 利用者側の視点から、現状の福祉サービスを評価するシステム。利用者さん達の苦情や不満を逃さずキャッチし、その質を向上させるのが目的です。練馬区障害者課と日本能率総合研究所が協力しています。 何故、「新しい」福祉なのでしょうか?それは「対等な」福祉だからです。例えばガイドヘルプ。これは障害者の皆さんが、相手となるヘルパーを選択できます。これ迄は障害者の方は選ばれるだけの立場でした。第三者評価システムも同様に、障害者の意見が取り上げられるものです。「今までに無い権利が出来た」と矢吹さん。 |
|
(2)障害者と施設 現在、日本では約12万人(18歳以上)の障害者の方が、東京から離れた郊外で生活しているといわれています。宮城県知事が「脱施設宣言」を出したと矢吹さんが教えてくださいました。そういった施設では経済・効率面での現実的な課題があります。しかし、それを越えればこの様な宣言も出来るのです。東京都も施設の中に競争を取り入れ、活性化を図ろうとし、また民間やNPOも色々な面で協力しているそうです。 |
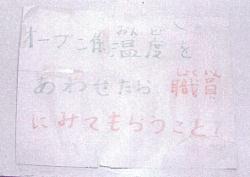
|
|
(3)「対等」ということ 障害者に対する偏見は未だに残っています。前述のシステムも、ごく当たり前の様に思えるが「これ迄は、障害者がヘルパーを選ぶ事は全く出来なかった(矢吹さん)」のです。そこには、やはりミゾがあったからだとしか思えません。 「そこに人間としての存在がある。共に暮らし、対等になろう」と矢吹さんはおっしゃいました。現在も確実に残る差別や偏見。しかし、私は今回訪問した「かすたねっと」で、それを忘れてしまいました。ここでは同じフィールドで、皆が同じ様に、明るく笑いながら働いているのです。まさに「対等」にお互いが接しているのです。「練馬」という地域の中で、楽しげに活動している皆さんと会って、私は嬉しくなりました。これがもっと広まったら…! 今回、矢吹一夫さんに福祉のお話を伺って、新しい福祉の視点が開けたのを嬉しく思います。矢吹さん、ありがとうございました。 《参考資料》 広報誌 かすたねっとNEWS vol.45,46 かすたねっと ホームページ http://www.fukusisagyosyocastanet.com |

|
| 4 「かすたねっと」の人々 |
|
(1)かすたねっとの人々 有志の方が「おかしや屋パレット」ねりまを開設してから17年近くが経とうとしています。現在勤めている利用者の中での最長勤務者は17年にもなるそうです。開設してから毎年1、2人程度増やしてゆき、現在では15人の利用者が働いています。 店長の矢吹良子さんは夫と息子が一人います。夫である矢吹一夫さんは勤めている時にもボランティアとして店を手伝っていたそうです。息子が成人し、定年退職した後に「これだけで食っていける」と考え本格的に参加して、現在では外回りを中心に、「かすたねっとNEWS」発行、かすたねっとHPの運営等を中心に活動しているそうです。 |

|
|
(2)かすたねっと店長の理念 かすたねっとの店長である矢吹良子さんの息子さんは障害を持っています。幼少時代に息子を通わせていた学校での体験が、今のかすたねっとでの理念の基となっているように思われます。 私達の間には『障害者は養護学校』という認識があります。実際、現在その認識通りに大半の障害児が一般の学校ではなく養護学校へ就学しています。 矢吹さんの息子さんは養護施設ではない施設に通っていたそうです。その施設の教育理念を理解するまでは時間がかかった、と矢吹さんは語っています。その学校では、一般学校で行うようないわゆる「勉強」はほとんど行われず、その代わりに「生活していくのに必要な事」を学ばせる事を中心としていました。自宅では家の手伝いを一人でやらせるように指示され、学校では例え泳ぎ方を知らなくてもプールに突き落とされ泳ぐ事を強要されたり、長距離のマラソンをさせられていました。年に4回は合宿があり、肉体的にも精神的にも徹底的に鍛えられたそうです。 |
|
最初、矢吹さんはこの教育方針に反対でした。「なんでこの子にこんなひどいことをさせようとするのか」と抗議しました。しかし先生方は「今こういうことをやらないと、将来絶対親が困るんですよ」と返しました。確かに、親がいるうちはまだ良いけれども、亡くなり障害者の子供だけが残された場合、果たしてその子は一人で生きていけるでしょうか? 矢吹さんはそう思い、次第に先生方の教育理念に共感していきました。 その理念はかすたねっとでの利用者達の接し方に現れています。かすたねっとでは、まず一人一人が「これはできる」という仕事を見つけることから始めていました。「クッキー製造や、袋詰め作業など、何でもよいから見つけてそれに従事させます。そうすれば自信がつき、意欲も湧きます。主旨は『できるようになること』」と矢吹さんは仰っていました。 また、矢吹さんは現在の養護学校と障害者を持つ親の姿勢についても論じていました。かすたねっとに勤めている利用者は養護学校卒業生もいますが、慣れてやる気を出すまでは時間がかかることもあるそうです。また、立ち作業が多い為、保護者から「こんな辛いことさせるなんて」と非難の声も出るそうです。矢吹さんは「ちゃんと成し遂げることができる力を持っているはずなのに、親の過保護さ等が妨げています。また、養護学校で『勉強』を教えていても、すぐに抜け落ちてしまい役に立ちません。必要なのは子供の自立の精神と社会で生きていく為の必要最低限の知識です」と仰っています。 矢吹さんの体験を踏まえ、的確なときに必要な支援をしていこうという気持ちをうかがうことができます。 |
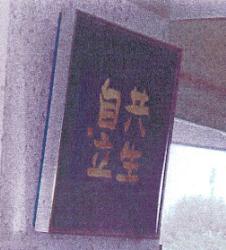
|
戻る